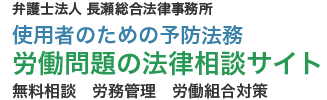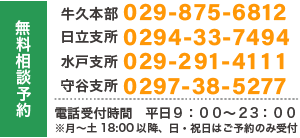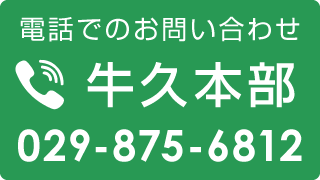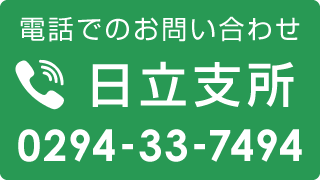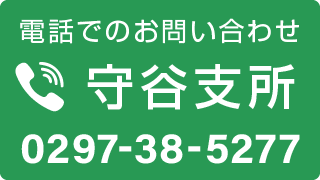Archive for the ‘コラム’ Category
社会保険労務士への弁護士によるサポート:将来を見据えた業務展望
社会保険労務士の皆様へ、弁護士が提供する社労士業務サポートの重要性を考えてみましょう。
1. 社会保険労務士業界の現状
社会保険労務士資格は、合格率6〜7%の難関試験であり、労働問題の専門家としての需要が高まっています。特に、働き方改革や新型コロナの影響により、企業の人事労務は大きな課題となっています。インターネットの普及により、労働者も労働問題についての情報を手に入れやすくなり、適切な労務管理が企業の成長に欠かせない要素となっています。
2. 技術の進化と社労士業務
しかし、技術の進化により、社会保険労務士業務の一部がAIに置き換わる可能性が指摘されています。給与計算や社会保険手続きなどの定型業務がAIによって効率的に行われる一方で、弁護士業界でも既にAIによる契約書チェックが行われています。このような変化に対応するためには、社会保険労務士業務にコンサルティング的要素を組み込む必要があります。
3. 生き残るための社労士業務の進化
生き残るためには、定型業務だけでなく、企業ごとにカスタマイズしたコンサルティング業務が注目されています。経営者の悩みを聞き出し、個別のコンサルティングを行うことで、労務課題を発見し、適切な労務管理体制を構築する支援が求められています。また、就業規則の作成においても、企業の実態やニーズを考慮した戦略的なアプローチが重要です。
4. 弁護士の活用法
社会保険労務士の皆様にとって、弁護士の活用は有益な方法です。
- 労働紛争の際には、労務に詳しい弁護士の意見を取り入れることで適切な労務アドバイスが可能です。
- 弁護士と連携することで、労務問題をトータルで解決することができ、顧問先に安心感を提供できます。
- 弁護士の研修やセミナーに参加することで、スキルや知識をブラッシュアップし、より深い労務対応が可能になります。
5. 弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポート
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、「労務管理アドバイザー」として、社会保険労務士の皆様の業務をサポートしています。このプログラムでは、弁護士の専門知識を活用し、社労士業務のフォローやコンサルティングを提供しています。是非、ご検討いただき、新しい士業連携の姿を目指してください。
顧問契約・リーガルメディアのご案内
1. 顧問契約サービスのご案内
弁護士法人長瀬総合事務所は、企業法務や人事労務・労務管理にお悩みの企業に対し、実績とノウハウを活かした顧問契約サービスを提供しています。企業の成長を支える制度設計や紛争の予防・解決を通じて、法律の専門性を提供しています。
2. リーガルメディアのご案内
弊所が運営する「企業法務リーガルメディア」は、企業法務や人事労務・労務管理に関連する情報を提供しています。企業の成長と労働問題対策をサポートします。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
労務管理アドバイザー:士業の先生方向けの専門サポート
士業の皆様へ、社会保険労務士・税理士・行政書士など専門分野の先生方向けに特化した「労務管理アドバイザー」をご紹介いたします。私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、企業法務や人事労務・労務管理にお悩みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウを持っています。
労務管理アドバイザーの役割
専門分野の先生方も、時にはアドバイスに迷うことがあるかと思います。そんなとき、私たちの労務管理アドバイザーが先生の事務所の顧客サービスを最大限にサポートいたします。企業からの法律相談や労務紛争の具体的な相談に対応し、迅速かつ的確なアドバイスを提供します。私たちはあなたの事務所を「いつでも・すぐに」フォローする「お抱えの弁護士」の存在となり、最大限のバックアップをお約束します。
労務管理アドバイザーのメリット
① サービス強化とブランディング
私たちの弁護士がアドバイスを提供することで、顧問先へのサービスを強化し、先生の事務所のブランド価値を高めます。法律問題が発生すれば迅速な対応が可能です。
② 事務所経営の不安軽減
労務専門の弁護士が常に電話やメールで相談に応じ、事務所経営に関する不安を軽減します。専門家のアドバイスで心理的負担や不安を和らげます。
労務管理アドバイザー契約の特典
労務管理アドバイザー契約には以下の特典が含まれます。
1. 随時無料相談
電話・メールでの法律相談が可能です。些細な問題から重要な相談まで、専門家のアドバイスを受けることができます。
2. 優先相談+相談料無料
込み入った相談に優先的に面談予約ができ、相談料も無料です。専門家のアドバイスをご自身のブランディングに活用できます。
3. 書面作成・リーガルチェック
文書作成やチェックを無料または割引で提供し、労使トラブルを予防します。
4. 顧問契約限定対応案件
就業規則作成・チェック、労働組合交渉対応などを労務管理アドバイザー限定でサポートします。
5. トラブル対応と弁護士費用割引
トラブル化した場合の迅速な対応と弁護士費用の割引があります。
プランと費用
詳細なプランと費用についてはPDFファイルをご参照ください。
実績と顧問契約締結の流れ
茨城県内や北関東の事務所様との実績を通じて、労使トラブルの予防や解決に貢献しています。顧問契約締結までの流れも分かりやすく案内しております。
お問い合わせは問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。顧問契約のご依頼を選択してご連絡ください。
顧問契約・リーガルメディアのご案内
ご紹介した内容に興味がある場合や、法律情報をより深く知りたい場合は、以下のリンクをご覧ください。
下記のサイトでは、労務問題に関する情報を提供しています。
ご質問やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。弁護士法人長瀬総合法律事務所があなたの事務所をサポートいたします。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
採用内定の取り消しに関する労務トラブル
相談内容
私は人事部で新卒採用の担当をしています。内定を出していたAさんがSNSで不適切な発信をしていたことが分かり、内定を取り消すことにしました。しかし、Aさんから内定の取り消しを問題にして請求される可能性があるとメールが届きました。採用内定の取り消しは違法なのでしょうか?
回答
採用内定によっては労働契約が成立しています。もしその内定を正当な理由なく取り消す場合、違法な内定の取り消しとなる可能性があります。Aさんが労働者としての地位を確認し、内定の取り消しを問題にして請求する可能性があります。さらに、慰謝料などの賠償請求も考えられます。
解説
1. 採用内定と労働契約の関係
採用内定は、法的には「始期付解約権留保付労働契約」とされます。つまり、採用内定によって労働契約が成立し、内定者も労働者とみなされます。内定が出されてから正式な入社日までの期間、内定者は一種の労働契約上の関係にあります。
2. 内定の取り消しは解雇に類似
採用内定の取り消しは、既に成立している労働契約を一方的に解約することになります。このため、解雇権濫用法理の規制が適用され、違法な内定の取り消しは認められません。内定者にとっては、突然の内定の取り消しは将来の人生設計に大きな影響を及ぼす可能性があります。
3. 取り消しの違法性と損害賠償
内定の取り消しには正当な理由が必要です。通常、内定通知書や誓約書に内定取り消しの取消事由が記載されています。内定取り消しの違法性は、その取り消し理由が客観的に合理的であり、社会通念上相当かどうかによって判断されます。違法な内定の取り消しに対して、内定者は労働者としての地位を主張し、損害賠償などを求める可能性があります。
4. 内定取り消しの検討と弁護士の相談
採用内定を取り消す際には、内定取り消しの取消事由が適用されるかどうかを慎重に検討する必要があります。特に、採用内定中の特有の取消事由が適用されるかどうかを確認することが重要です。弁護士の助言を受けながら、適切な判断を行うことが必要です。内定者との協議も重要であり、双方が納得する解決策を模索するべきです。
総合的に言えば、採用内定の取り消しは法的なリスクを伴う行為であり、適切な判断と弁護士のアドバイスを受けることが重要です。特に、採用内定に関する専門知識を持つ弁護士の助言を得ることで、違法性を回避し、適切な対応を行うことができるでしょう。
顧問契約・リーガルメディアのご案内
顧問契約サービスのご案内
当事務所は企業法務や労務管理に豊富な実績と専門知識を持っており、紛争の解決だけでなく予防策や制度設計のサポートも行っています。顧問契約サービスの詳細については、弊所ウェブサイトの下記をご覧ください。
リーガルメディアのご案内
企業法務や労務管理に関連するお悩みは、当事務所が運営する「リーガルメディア」で詳細な情報を提供しています。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
労使トラブルを未然に防ぐための顧問契約のおすすめ
労働問題は経営において大きなリスクです。労使トラブルは経済的な損失、人的対応リスク、企業の評判低下などを引き起こします。解決に手間とコストがかかるため、事前の対策が重要です。
労働弁護士の顧問契約で労使トラブルを防ぐ方法
顧問契約の重要性
労働問題を未然に防ぐために、労働弁護士との顧問契約を検討しましょう。顧問契約により、労働問題に強い専門家の支援を受けることができます。
中小企業も注意が必要
労使トラブルは大企業だけの問題ではありません。中小企業や個人事業主も巻き込まれる可能性があります。むしろ、こうした企業ほど長期間にわたる潜在的リスクを抱えていることもあります。
顧問契約のメリット
顧問契約のメリットは以下の通りです。
- かかりつけ専門家の利用
顧問契約で労務管理の専門家が常に身近にいるため、法律相談がいつでも可能です。メールや電話での相談も受け付けています。 - 経営者の不安解消
顧問弁護士の存在により、法律の根拠に基づいた対応ができるため、経営者や人事担当者の不安を解消します。 - コストパフォーマンス
法務部を設置するコストと比べて、顧問契約はコスト効果が高いです。法律相談や書面作成を通じて紛争を防止することが可能です。
1. 特典と費用
顧問契約には次の特典があります。
- 随時相談
通常の法律事務所と異なり、顧問契約を結ぶと随時電話やメールでの相談が可能です。些細な問題でも気軽に相談できます。 - 優先相談と無料時間
顧問先企業は優先的に面談相談を予約できます。また、一定の範囲で相談料が無料となります。 - 書面作成とリーガルチェック
社内文書や従業員に対する書面の作成やチェックが労使トラブルを予防するために重要です。顧問契約では、この作業が割引又は無料となります。 - 労使トラブル対応の優遇
実際のトラブル発生時にも弁護士費用が割引となります。
2. 実績の一例
顧問契約により労使トラブルを未然に防いだ事例として、賃金体系見直しや労働者の退職・解雇に関する対応があります。
3. 締結の流れ
顧問契約を検討する場合、まずは面談による企業ヒアリングがあります。その後、適切なプランと費用が提案され、契約が締結されます。
顧問契約により、労使トラブルのリスクを最小限に抑え、経営の安定を図ることができます。詳細な情報はPDFファイルをご覧いただくか、問い合わせフォームからお問い合わせください。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
建設業界で労務問題に直面している経営者の方へ
建設業界で労務問題に直面している経営者の方へ
建設業界は社会基盤の構築・維持という重要な役割を果たす産業です。地域の安全確保や復興においても大きな役割を果たしています。建設業界は市場規模や投資の動向において変化があり、近年は復興需要や民間投資の増加が見られる一方で、労働力の確保や労働条件の改善といった課題にも直面しています。
労働力確保の課題は、若年層の入職者不足と高齢化による引退者増加が顕著です。さらに、長時間労働や休日の取得の少なさといった課題も浮上しており、業界全体で働き方改革が求められています。また、労働災害における死亡事故が業界別で最多となるなど、安全への取り組みも不可欠です。
建設業特有のリスクも存在し、賠償責任や工事遅延、設計・施工の問題など、法的なリスクを適切に管理する必要があります。特に、長時間労働による未払残業代請求や労働災害リスク、他業種と異なる業務形態に伴うリスクも重要なポイントです。
労働力確保と働き方改革の課題
建設業界は、若年層の入職者が減少しており、高齢化が進行しています。これにより、引退者が増える一方で、中長期的な労働力の確保が難しくなっています。また、週休2日制の浸透が低く、休日の取得が少ないことや、長時間労働が一般的であることが課題となっています。
労働災害リスクと安全対策
建設業界は、死亡事故につながる労働災害が多発しており、その発生率が他の業界よりも高い傾向があります。建設現場での作業は危険が伴うことが多く、労働安全の確保が喫緊の課題です。適切な安全対策の実施や労働者への教育・訓練が重要です。
建設業特有の法的リスク
建設業界では、多数の業者が関与するプロジェクトにおいて、賠償責任リスクや工事遅延リスク、性能リスクなどが存在します。特に、多様な業者の連携や指揮系統の確立が難しいことから、契約や責任の明確化が求められます。
長時間労働と未払残業代請求のリスク
建設業界では、休日の取得が少なく、長時間労働が慢性化しています。これにより、労働者から未払残業代請求が発生するリスクが高まっています。労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効期間が延長され、適切な労働時間管理が求められます。
パワーハラスメントの問題
建設現場では、ストレスや圧力の高い環境で働くため、パワーハラスメントが発生するケースも多いです。労働者同士のトラブルや不当な扱いによる心身の負担は、労働力の健全な維持に影響を与える可能性があります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、建設業界の法的な課題に専門知識を持つ弁護士が対応しています。例えば、長時間労働に関するアドバイスや未払残業代請求のリスク回避、労災対応、パワーハラスメント事案の対応など、幅広いトピックに対応しています。
長瀬総合の労務コンサルティング
労務応援コンサルティングでは、以下のようなサポートを提供しています。
- 建設業特有の日常労務・法務アドバイス
- 雇用契約書や就業規則の整備
- 書面や契約関係のチェックと作成サポート
- 労使紛争予防のための制度作り
- 労使紛争時の迅速な代理対応サポート
私たちは、建設業界における労務問題に精通し、企業の安全や成長をサポートすることを使命としています。詳細な情報やサービス内容については、弁護士法人長瀬総合法律事務所のウェブサイトをご参照いただくか、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
教育業界で労務問題に強い弁護士をお探しの経営者の皆様へ
教育業界の皆様へのメッセージ
教育業界は、国の発展に欠かせない基盤です。私たちの国では資源やエネルギーが限られているため、人材の育成が特に重要な課題となっています。私立・公立学校、大学、塾、予備校など、教育を提供する機関は、将来の人材を育む大きな役割を果たしています。
教育業界の現状
現在、教育業界は様々な変化の中にあります。少子化や新型コロナウイルスの影響などにより、市場は変動しています。一方で、EdTech(エドテック)などのICTを活用した教育技法の導入が進む中、教育の方法やアプローチも変わりつつあります。また、政府の支援により、人材開発の重要性が増しています。
対応すべき労務問題
教育業界では労務問題にも目を向ける必要があります。生徒や保護者とのトラブル、労働時間の管理、教員の働き方改革などが重要なテーマです。生徒や保護者との対応は企業の評判やイメージに影響を与えるため、慎重な対応が求められます。また、教員の働き方改革も重要であり、労務管理や職場環境の整備が必要です。さらに、教育のノウハウや資材の保護、競業避止義務や秘密保持義務の確保も欠かせません。
労務トラブルへの対応事例
私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、教育業界における労務問題に豊富な経験を持っており、以下の事例からもご対応できることをご紹介します。
- 長時間労働の改善: 教育機関での未払い残業代や労働時間の適正管理に関するコンサルティングを行い、労働トラブルの予防・解決を支援します。
- 競業避止義務や秘密保持義務: ノウハウや教材の保護を確保するための適切な契約書作成やアドバイスを提供します。
- 教育ノウハウの保護: 他社へのノウハウ流出防止のために、競業避止契約や秘密保持契約の整備を行います。
- 労務紛争の解決: 教員の雇用契約や労働時間に関するトラブルに対して、迅速な代理対応を行い、労働紛争のリスクを最小限に抑えます。
私たちの労務応援コンサルティング
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、教育業界の労務問題に特化したサポートを提供しています。
- 教育業界に特化した労務・法務アドバイス
- 雇用契約書や就業規則の整備
- 書面・契約関係のチェック・作成対応
- 労働トラブル予防のための制度作り
- 労働紛争への迅速な代理対応
教育業界における労務問題に関するサポートを通じて、お客様の事業の発展と労働環境の改善を支援いたします。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
労務管理における管理職のポイント
相談内容
当社は全国に数多くの支店を展開しており、各支店の店長は重要な管理職として活躍しています。最近、A支店の店長が残業代を請求してきました。ただし、店長は管理職としての役割を果たしており、残業代を支払う必要はないと考えています。
重要な視点
「管理職」という立場が、労働基準法で規定されている「管理監督者」と同一視されるわけではありません。実際、「管理監督者」の地位になるケースは稀です。ですから、管理職であるからといって、適切な労務管理が不要というわけではありません。
多い相談事例(業界別)
- 建設業
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸・郵便業(トラック運送業)
- 卸売・小売業
- 金融業・保険業
- 不動産・物品賃貸業
- 宿泊・飲食業(ホテル・飲食店等)
- 教育・学習支援(塾・予備校等)
- 医療・介護福祉業 ☑サービス業
※実際、管理職や役員の名称があるにも関わらず、実質的には名ばかりの場合があります。この問題は特に宿泊・飲食業(ホテル・飲食店等)、卸売・小売業、教育・学習支援(塾・予備校等)で顕著ですが、幅広い業種で相談が寄せられています。
「管理監督者」とは?
管理職の労務管理には独自の問題が存在します。労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」(通称:管理監督者)は、労働時間や休息、休日に関する法規制の対象外とされます。従って、管理監督者には労働時間の制限や休憩・休日の保障は適用されません。したがって、残業代の支払いも義務づけられません。管理職が「管理監督者」として認定されるかどうかは、労務管理の重要なポイントとなります。
「管理職」は必ずしも「管理監督者」ではない
実際には、支配人、支店長、店長、部長など、企業によって「管理職」のポジションが異なります。ただし、企業が定めた「管理職」全てが労働時間などの規制から免れ、残業代を支払わなくて済むわけではありません。なぜなら、「管理監督者」であるかどうかは単に職名だけで判断されるものではないからです。実際の業務内容や権限、責任、勤務スケジュールなどの要素が判断材料となります(昭和63年3月14日基発150号)。
「管理監督者」の判断要件
「管理監督者」であるかどうかは、以下の3つの要素で判断されます。
職務内容、権限、責任の重要性
経営方針への関与度や労務管理の権限が重要です。経営に関わる権限を持ち、労務管理にも関与するようなポジションが「管理監督者」に近いです。
勤務態様と労働時間の裁量
勤務の仕方や労働時間を自ら決定する権限がある場合、「管理監督者」に近い状態です。タイムカードの管理がないか、出勤・退勤に柔軟性があるかも重要です。
適切な報酬
「管理監督者」としての待遇が適切であることが求められます。残業代などが免除される代わりに、十分な報酬が支給される必要があります。
管理職・役員の労務管理には専門家の助言が必要
「管理監督者」の位置づけは、単に名前だけでなく、実務的な経営的立場が重要です。特に、プレーイングマネージャーのような現場担当者は、一般的に「管理監督者」には該当しません。言い換えれば、「管理職」であるからといって、安易に残業代を支払わない判断はリスクを伴います。万一、労働審判や民事訴訟の対象になり、巨額の賠償金を支払う可能性があります。
労働問題を未然に防ぐためには、専門の労働弁護士に相談することをおすすめします。正確な労務基準の適用や適切な労働時間の管理のために、専門家のサポートは不可欠です。お気軽にご相談ください。
労働問題総合相談サイトでは、労働トラブルの予防に全力でサポートします!
また、トラブルを未然に防ぐためには、継続的なサポートが重要です。顧問契約を検討することをおすすめします。解決事例もご覧ください。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
解雇の種類
相談内容
会社の立場として、従業員の解雇を考えています。ただし、解雇の理由は、業績不振や業務態度の問題など、多岐にわたります。
解雇にはさまざまなタイプがあると聞きましたが、解雇の種類によって法律の適用が異なるのでしょうか。
回答
まず初めに、会社が解雇を検討するかどうか、そしてその理由を特定することが重要です。
解雇には「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」という3つのタイプがあり、それぞれの妥当性が異なります。
解説
解雇とは何か~自主退職との違い
解雇の意味
解雇とは、雇用主が一方的に労働契約を終了させることを指します。反対に、労働者が自発的に退職する場合は解雇ではありません。
解雇には通知書や理由の証明書が提供されることがあり、これらの書類がある場合は解雇が明確です。しかし、実際には「解雇」と明言されていなくても、労働者が解雇されたと主張するケースも多いです。
解雇と自発的退職の区別
以下の場合を考えてみましょう。
- 例1)会社が急に「明日から出社しなくていい」「君の仕事はもうない」と告げて仕事を外された。
- 例2)会社が「もう君を雇い続けることは難しい。辞めるつもりなら辞めろ」と言って、労働者が会社に出てこなくなった。
- 例3)労働者が退職願を提出しましたが、「失業保険のために会社都合退職にしてほしい」と要望し、会社が離職の通知を送りました。
例1の場合、会社の強制力が強いため、解雇とみなされることが多いです。
例2は微妙です。労働者側にも退職の意思があり、解雇とは言えない可能性もあります。状況によって異なります。
例3の場合、労働者の退職意志は明確ですが、解雇の通知がどのように扱われるかは難しい問題です。
解雇されたか不明な場合は弁護士に相談!
会社から無理に仕事を止められた場合は、必ず解雇通知書や解雇理由証明書の提供を求めるべきです。
特に、解雇理由証明書は労働基準法の規定で提供が求められています。たとえそうした書類がなくても、対立を解決する手段は存在します。
ただし、状況は複雑ですので、労働問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。
解雇の種類
解雇には「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」という3つのタイプがあります。
それぞれの解雇には異なる理由や性格があり、そのために法律上の条件も違います。
これから詳しく見ていきましょう。
普通解雇とは
普通解雇は、労働者の業務遂行の不履行を主な理由とした解雇の一種です。
通常、就業規則に違反した場合に行われます。以下にいくつかの種類を挙げてみますが、詳細は参考サイトをご覧ください。
- 労働能力の低下
「身体・精神的な問題で仕事ができない場合」が一般的です。 - 能力不足・成績不良・適格性不足
仕事を遂行するための能力や適格性が不足している場合の解雇です。 - 業務怠慢・勤務不良
無断欠勤、遅刻・早退、業務への取り組みや態度の問題、チームでの協調性の欠如などが解雇の理由になることがあります。 - 職場の規律違反・不正行為・業務命令違反
日常業務の指示に従わなかったり、命令に背いたりする場合に問題が生じます。
整理解雇
整理解雇は、会社が経営課題や合理化のために人員を削減するために行われる解雇です。いわゆるリストラの一環です。
普通解雇とは異なり、無実の労働者でも会社から一方的に解雇されるため、その条件は厳格です。
整理解雇の妥当性を判断するためには、通常以下の4つの要件を満たす必要があります。
単に「経営が苦しいから解雇」というだけでは、要件を満たすのは難しいでしょう。
- 人員削減の必要性
余剰人員の削減が必要かどうかを検討します。近年の判例では、倒産の危機まで迫っている必要はないとされています。 - 解雇回避の努力
解雇は最終手段です。会社は、解雇を回避するための努力をしなければなりません。
具体的には新規採用停止、給与削減、時間外労働の削減、希望退職募集などがあります。 - 選択された解雇対象の妥当性
偏見に基づいて選ぶことは許されません。選択は合理的である必要があります。勤務評価や影響の少ない人物を選ぶことが妥当です。 - 労働者への説明・協議
会社は、解雇方針や理由などを労働者に説明する義務があります。
懲戒解雇
懲戒解雇は罰としての解雇です。普通解雇とは異なり、契約違反が主な理由です。
会社からの制裁として、従業員が解雇されることで、重大な影響を及ぼします。
懲戒解雇の効力を認める判断は普通解雇に比べて厳格ですので、懲戒解雇の検討には専門家の助言が重要です。
解雇を検討する企業は、早めに弁護士に相談を
解雇の判断は慎重に
解雇は生活に大きな影響を与えるため、慎重な判断が必要です。
また、無効な解雇に加えて、未払いの賃金を請求される可能性もありますので、経済的な影響も大きいです。
しかし、問題があっても、安易に解雇するのは危険です。数百万円以上の支払いが必要になるケースもあります。
専門家に相談する価値あり
先述のように、各解雇の種類は事実を検討し、契約書や就業規則などに基づいて法的な判断をすることが不可欠です。
解雇を検討する際は、事前の準備が必要ですが、労務問題に精通した弁護士の指導の下で適切な解雇が可能です。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、解雇理由が正当な場合、適切なプロセスを実施し、有効な解雇が裁判所で支持されるケースが多数あります。
解雇を検討する企業は、労働問題の専門家である弁護士に早めに相談することをお勧めします。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
法的な労働関係における解雇の要件とケース
ご相談
当社では、成績や勤務態度が悪い従業員の解雇を考えていますが、解雇ができる条件は限られているようです。解雇が可能な場合とはどのような場合なのか、教えていただけますか。
ポイント
解雇には法的な要件が厳しく設けられています。容易に解雇することはできません。労務の専門家である弁護士のアドバイスを受けつつ進めることをおすすめします。特に多い相談業種は以下の通りです。
- 建設業
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸・郵便業(トラック運送業)
- 卸売・小売業
- 金融業・保険業
- 不動産・物品賃貸業
- 宿泊・飲食業(ホテル・飲食店等)
- 教育・学習支援(塾・予備校等)
- 医療・介護福祉業
- サービス業
※業種にかかわらず、解雇に関する相談が多く寄せられています。
普通の解雇が可能な場合
労働契約法第16条は、合理的で社会通念上相当な理由がない限り、解雇できないことを規定しています。不当解雇を避けるための措置です。では、どのような場合に解雇が可能になるのでしょうか。以下にいくつかのケースを示します。
傷病・健康状態の悪化による労働能力の低下
このケースでは、従業員が業務をこなせないほど重篤な身体・精神の障害がある場合が考えられます。ただし、その程度は極めて重大で、労働が不可能な状態である必要があります。多くの企業では、休職制度を活用し、解雇前に休職や自然退職を検討します。
能力不足・成績不良・適格性の欠如
会社の業務に適切な能力や適格性を持っていない場合、解雇が検討されます。ただし、解雇の根拠は客観的な資料で裏付けられ、指導・注意による改善の機会も与えられている必要があります。
職務懈怠・勤怠不良
無断欠勤や遅刻、勤務態度の問題などが解雇の理由となります。これにも客観的な資料が必要で、会社の指導や改善措置の記録も重要です。
職場規律違反・不正行為・業務命令違反
上司や同僚への暴行・妨害などが含まれます。これは労働者の非違行為であり、重大な場合、直接的な解雇理由につながることもあります。ただし、事情を詳細に調査し、証拠を集める必要があります。
整理解雇における不当解雇
整理解雇は、特定の要件を満たす場合に行えるものです。次の4つの要件を満たす必要がありますが、その際には証拠資料が重要です。
① 人員削減の必要性があるかどうか
余剰人員を削減する必要があるかどうかを判断します。ただし、企業の倒産を回避するために必要とされる場合に限られません。
② 会社が解雇回避努力義務を行ったかどうか
解雇は最終手段であり、会社は他の選択肢を検討する義務があります。人件費削減策なども含めて、努力が求められます。
③ 解雇される人物を選んだことに相当性があるか
解雇される従業員の選定は恣意的でないことが求められます。合理的な基準で選定される必要があります。
④ 労働者・労働組合への説明・協議を十分におこなったか
解雇の意思決定プロセスを透明に説明し、従業員や労働組合との十分な協議を行う必要があります。
懲戒解雇における不当解雇
懲戒解雇は普通解
雇に比べて厳格な要件が求められます。解雇が有効かどうかは、従業員の言い分も聴きながら、慎重に検討する必要があります。
解雇の検討には労働弁護士のアドバイスが不可欠です。誤った解雇は労働審判や民事訴訟を引き起こす可能性があり、会社に多大なコストとリスクをもたらす可能性があります。解雇を検討する場合は、労働弁護士との協力をおすすめします。解雇を進める場合も含めて、労使トラブルを防ぐために顧問契約の締結をご案内しています。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
会社の労災対応・安全配慮義務について
ご相談
会社の従業員が工場で怪我をした際に、労災保険を使って対応しました。しかし、その後損害賠償の請求がありました。労災保険が賠償された後に、なぜ会社が責任を負う必要があるのか疑問に思います。
重要なポイント
- 労災保険で迅速な対応は大切だが、安全に対する配慮が不足している場合、民事上の賠償責任が問われることがある
- 賠償責任の額が増えることや会社のイメージへの影響も考慮し、労災問題には早めに専門の弁護士に相談することが重要
特に多い相談の業種
- 建設業、製造業、情報通信業、運輸・郵便業
- 卸売・小売業、金融業・保険業、不動産・物品賃貸業
- 宿泊・飲食業、教育・学習支援業、医療・介護福祉業、サービス業
- 長時間労働による労災の問題もあるため、多岐にわたる業種で相談が寄せられています。
労災保険の詳細
労災保険の内容
業務による労働者の怪我や病気などに対して、多くの損害がカバーされる。
- 療養補償給付:診察や薬、手術などの治療費用
- 休業補償給付:平均賃金の60%が支給される
- 障害補償給付:治療後の身体の障害に対する支給
- 遺族補償給付:労働者の死亡による配偶者や子供への支給
- 葬祭料給付:葬式費用の支給
- 傷病補償年金:治らない障害に対する給付
- 介護補償給付:介護が必要な場合の費用支給
会社側の労災対応
労災保険への加入は会社の義務であり、怪我をした労働者が治療に専念できるように迅速な手続きが必要
- 「労災隠し」は許されず、積極的な協力が必要
以上の点を考慮して、労災保険の適切な管理と早期の専門家への相談が重要であることがわかります。
会社にとって労働災害、一般に労災と呼ばれるものは深刻な問題です。労災が起きた場合、以下のようなリスクが生じることが一般的です。
多額の賠償責任
労働災害が発生すると、会社は労働者から多額の損害賠償を請求されることがあります。多くの人が、「労災保険でカバーされるのでは?」と考えることが一般的ですが、労災保険の支給範囲は限られています。例えば、慰謝料が支給されない、休業補償が全額ではない、将来の収入補填がないなど、完全に損害をカバーできないため、会社は大きな賠償責任を負うことになることがあるのです。
企業イメージの低下
企業の安全管理が厳しく見られる昨今、労災が起きると企業のイメージが低下することも珍しくありません。特に労働者が過労死や自殺に至った場合、企業は社会的な非難を受けることがあります。これは大手企業に限らず、小規模企業にも言えることで、労働安全に問題があるというイメージは長く残ることがあるのです。
労災を未然に防ぐためには、安全衛生管理の徹底が重要です。最新の保険商品が民事賠償責任をカバーするものも出てきていますが、それだけでは十分ではありません。会社としては、安全配慮義務を尽くし、事故の防止に全力を尽くすべきでしょう。専門家のアドバイスを受け、体制を見直していくことも重要な一歩です。
労災事故が特に起きやすい業種の企業の方々には、弁護士への相談をお勧めします。事前予防のための弁護士の利用や、労災事故が起きた場合の弁護士のサポートが不可欠です。リスクを避け、適切な労働安全管理を行うために、労働実務を踏まえた判断・手続きが必要です。法的な労務管理の専門家、労働弁護士に相談することが、そのための最良の方法でしょう。
企業のために労使トラブルを防ぐ支援を行うサイトや、労使トラブルを万全に防ぐための顧問契約などもありますので、これらのサービスを活用することも選択肢の一つかもしれません。何よりも大切なのは、労働災害を未然に防ぐための体制作りと、社員一人一人の健康と安全への配慮です。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube
« Older Entries Newer Entries »