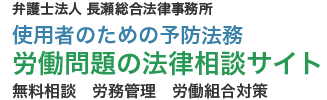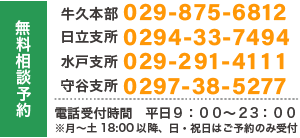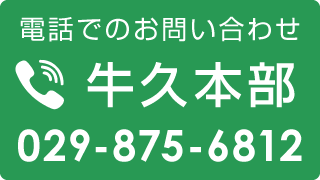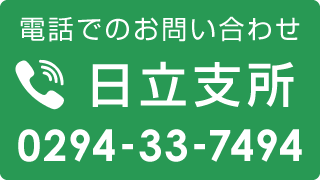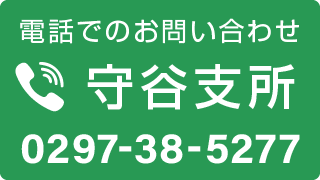Archive for the ‘更新情報’ Category
【コラム公開】アルバイト募集と年少者(未成年)雇用の法的ポイント|労働時間・深夜業・危険業務の制限を解説
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ アルバイト募集と年少者(未成年)雇用の法的ポイント|労働時間・深夜業・危険業務の制限を解説
人手不足が深刻化する中、多くの企業において、学生アルバイトなどの若年層労働力への期待が高まっています。特に繁忙期や土日のシフトを埋めるために、高校生を含む未成年者の採用を検討される経営者様や人事担当者様も多いのではないでしょうか。
しかし、未成年者(特に満18歳未満の「年少者」)の雇用に関しては、労働基準法において成人とは異なる厳格な保護規定が設けられています。これらの規制は、未成熟な若年者の健康と福祉を守るためのものであり、違反した場合には刑事罰を含む厳しい処分が科される可能性があります。また、建設業や製造業においては、危険有害業務への就業制限も厳しく定められており、知らずに業務に従事させた場合、重大な労働災害やコンプライアンス違反につながるリスクがあります。
本稿では、企業がアルバイトとして年少者(未成年)を採用・雇用する際に押さえておくべき法的留意点、特に労働時間の制限、深夜業の禁止、そして契約時の注意点について、実務的な観点から解説します。
【コラム公開】日雇い派遣の原則禁止と厳格な例外要件
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 日雇い派遣の原則禁止と厳格な例外要件|人事労務・労務管理
「明日1日だけ人手が欲しい」「今週の繁忙期だけ、臨時のスタッフを確保したい」といった需要は、多くの企業が日常的に直面する課題です。かつては、こうした超短期の需要に対し「日雇い派遣」が広く利用されていました。
しかし、日雇い派遣は、労働者の雇用が不安定であり、労働災害の防止や安全衛生教育が困難であるといった問題が指摘されたため、2012年の労働者派遣法改正により、日雇い派遣(日々または30日以内の期間を定めた派遣)は原則として禁止されました 。
この原則禁止のルールを知らずに、あるいは「例外要件」を誤って解釈したまま日雇い派遣を受け入れた場合、派遣先企業は行政指導の対象となるだけでなく、意図せず派遣労働者を直接雇用する義務を負う「労働契約申込みみなし制度」 という重大な法的リスクに直面します。
本稿では、日雇い派遣に関する厳格な法的制限と、適法に活用できる「例外要件」について解説します。
【コラム公開】紹介予定派遣の導入と(廃止された)特定派遣の法的留意点
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 紹介予定派遣の導入と(廃止された)特定派遣の法的留意点|人事労務・労務管理
人材の流動化が進む現代において、企業が自社の文化や業務に真に適合する人材を採用することは、ますます困難になっています。「紹介予定派遣」は、このような採用における「ミスマッチ」を防ぐための有効な手段として注目されています。一定期間「派遣」として実務を経験してもらった上で、直接雇用(正社員や契約社員)に切り替えるかどうかを判断できるため、企業・労働者双方にメリットがあります。
一方で、かつて派遣の一形態であった「特定派遣」は、2015年の労働者派遣法改正により廃止されました。この「特定派遣の廃止」という法改正は、過去の出来事であると同時に、現在の派遣先企業(受入企業)のコンプライアンス・リスクに直結する重要な法的教訓を含んでいます。
本稿では、「紹介予定派遣」の適切な運用方法と法的な留意点、そして「特定派遣の廃止」がもたらした派遣先リスクについて解説します。
【コラム公開】労働者派遣法の基本ルールと3年制限|人事労務・労務管理
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 労働者派遣法の基本ルールと3年制限|人事労務・労務管理
労働者派遣は、企業が人手不足の解消や専門スキルの確保、業務の繁閑に対応するために活用する、重要な経営戦略の一つです。しかし、派遣労働は「雇用する者(派遣元)」と「指揮命令する者(派遣先)」が分離するという特殊な雇用形態であるため、労働者保護の観点から「労働者派遣法」(以下「派遣法」)によって厳格なルールが定められています。
特に、派遣の受け入れ期間に関する「3年ルール」や「抵触日」の管理は極めて重要です。これらのルールを正しく理解せず、安易に派遣労働者を受け入れていると、行政からの指導や罰則の対象となるだけでなく、「労働契約申込みみなし制度」 という、派遣先が意図せず派遣労働者を直接雇用する義務を負うという重大なリスクに直面する可能性があります。
本稿では、派遣法の基本構造、特に「3年ルール」の正確な理解と、派遣先企業が負うべき法的責任について、実務上の留意点を中心に解説します。
【コラム公開】パートタイム・短時間労働者の待遇と「同一労働同一賃金」
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ パートタイム・短時間労働者の待遇と「同一労働同一賃金」
パートタイマーや有期雇用契約者(以下、総称して「パート・有期労働者」)は、多くの企業において基幹的な労働力として不可欠な存在です。しかし、長年にわたり、正社員(無期フルタイム労働者)との間に存在する不合理な待遇格差が社会問題とされてきました。
この問題に対応するため、「パートタイム・有期雇用労働法」(以下「パート有期法」)が施行され、「同一労働同一賃金」の原則が法的に義務化されました。これにより、企業は正社員とパート・有期労働者との間の待遇差について、合理的な説明ができない限り、その格差を解消しなくてはならなくなりました。
特に、2020年に相次いで示された最高裁判決 は、賞与や退職金といった中核的な待遇差に関する司法の判断基準を明確にしました。本稿では、企業が「同一労働同一賃金」に適切に対応するために何をすべきかを、法務・労務の観点から解説します。
【コラム公開】有期雇用契約の締結と更新
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 有期雇用契約の締結と更新
企業が従業員を雇用する際、有期雇用契約は、プロジェクト単位での人材確保や、経営状況に応じた柔軟な人員調整を可能にする点で、多くのメリットを有します。正社員(無期雇用契約者)とは異なり、契約期間の定めがあるため、期間満了と共に雇用関係が終了することが原則となります。
しかし、この「期間の定め」があるという特性は、同時に法的なリスクも内包しています。特に、契約更新が反復・継続された場合に従業員側に生じる「更新期待権」や、労働契約法の改正によって導入された「無期転換ルール(通称5年ルール)」は、企業が意図しない長期雇用や、雇止め(契約の更新拒否)をめぐる紛争に発展する火種となります。
有期雇用契約の管理を適切に行わなければ、「期間満了だから」という理由だけでは契約を終了させることができず、企業経営に予期せぬ制約がかかる可能性があります。本稿では、有期雇用契約の締結と更新に際して企業が直面する法的リスクと、最新の裁判例を踏まえた実務的な防止策について解説します。
【コラム公開】ハラスメント相談窓口の設置と運営方法
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ ハラスメント相談窓口の設置と運営方法
セクハラやパワハラ、マタハラなどのハラスメント行為は、被害者に深刻な精神的ダメージを与え、企業経営にも大きなリスクをもたらします。ハラスメントを未然に防ぎ、また発生した場合に迅速に対処するには、従業員が気軽に相談できる「ハラスメント相談窓口」を整備することが不可欠です。
本記事では、ハラスメント相談窓口をどのように設置し、どのような運用をすべきか、企業側が注意すべきポイントを解説します。適切な窓口運営を行うことで、早期対応・被害拡大防止が可能となり、企業の信頼を守るうえで重要です。
【コラム公開】職場での言動・指導とパワハラ認定の境界
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 職場での言動・指導とパワハラ認定の境界
職場での指導や叱責は、業務を円滑に進め、従業員を育成するうえで不可欠なものです。しかし、厳しい指導が「パワハラ」にあたるかどうかは非常に敏感な問題であり、指導する側とされる側の認識が食い違い、深刻なトラブルを引き起こすケースが多々あります。パワハラ防止法が施行された今、企業としては「正当な業務指導」と「パワハラ」との境界を明確に把握し、従業員への周知や管理職の教育を徹底しなければなりません。
本記事では、職場での言動や指導がどのような場合にパワハラ認定される可能性があるのか、適法な指導と違法なパワハラの境界線、そしてトラブルを防止するポイントなどを解説いたします。
【コラム公開】パワハラ防止法に基づく企業の義務
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ パワハラ防止法に基づく企業の義務
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐために、2020年6月に施行された「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」は、企業に対してパワハラ防止措置を講じる義務を明確にしています。これにより、相談窓口の設置や被害者・加害者への対応ルールの策定など、具体的な取り組みが企業に求められるようになりました。
本記事では、パワハラ防止法が企業に課す義務内容や、対策を怠った場合のリスク、実務上の注意点などを詳しく解説します。弁護士法人長瀬総合法律事務所が多数のパワハラ相談・紛争を解決してきた経験を踏まえ、わかりやすい情報をまとめていますので、パワハラ対策強化にお役立てください。
【コラム公開】セクハラ・マタハラの防止措置
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ セクハラ・マタハラの防止措置
セクシャルハラスメント(セクハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)は、職場において依然として根深い問題となっています。従業員が被害を受けるだけでなく、企業が社内不祥事として大きく信用を失う事例も少なくありません。さらに、近年の法改正により、事業主にはハラスメント防止策を講じる義務が明確化され、対応を怠れば行政指導や社名公表などのリスクがあります。
本記事では、セクハラ・マタハラの具体的事例や法的責任、そして企業が防止措置として整備すべき体制を詳しく解説します。自社のセクハラ・マタハラ対策を強化したい企業のご担当者は、ぜひ参考にしてください。
« Older Entries