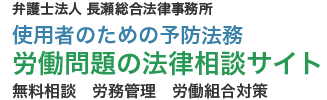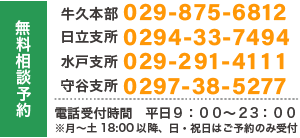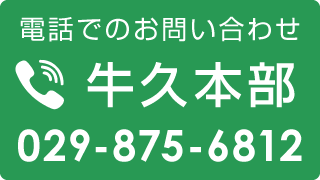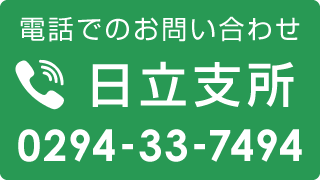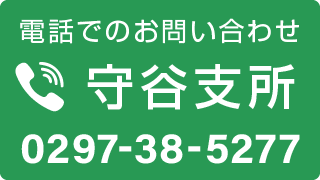Archive for the ‘更新情報’ Category
【コラム公開】休憩時間・中抜け制度の運用
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 休憩時間・中抜け制度の運用
労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも1時間の休憩を与える義務を定めています。休憩時間は労働から離れ、自由に利用できることが原則です。しかし、実際の現場では休憩時間を十分に取れなかったり、「中抜け」で一旦業務を離れ、後で労働時間を再開するような働き方もあり、管理上のトラブルが起こりやすい領域です。
本記事では、休憩時間の基本ルールや、「中抜け制度」を導入する場合の注意点、休憩管理をめぐるよくあるトラブル事例などを解説します。法的視点と実務経験を踏まえてまとめていますので、企業の労務担当者の方はぜひ最後までご覧ください。
【コラム公開】労働時間の客観的把握義務
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 労働時間の客観的把握義務
労働時間の管理は、企業が労働基準法を遵守するうえで非常に重要なテーマです。近年の働き方改革により、「労働時間の客観的な把握義務」が強調されるようになりました。従業員自身による自己申告だけに頼る管理方法では、サービス残業や長時間労働の見落としが発生しやすく、未払い残業代請求や行政指導につながるリスクが高まります。
本記事では、労働時間を客観的に把握する具体的手法や、自己申告制の問題点、導入可能なシステムや記録手段などを紹介します。企業がとるべき対策を解説いたしますので、自社の勤怠管理を再確認する機会として、ぜひお役立てください。
【コラム公開】時間外労働の上限規制
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 時間外労働の上限規制
働き方改革関連法が施行され、時間外労働(いわゆる残業)の上限が法令で厳格に規定されました。従来、36協定を締結すれば事実上青天井で残業させられるように思われていましたが、今では「原則月45時間、年360時間」「特別条項を使っても年720時間」という数値が設定され、これを守らないと行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
本記事では、時間外労働の上限規制に関する基本的なルールや、特別条項の導入要件、上限違反が起こるとどうなるかなどを解説します。企業が注意すべきポイントを分かりやすくまとめましたので、ぜひ今一度自社の残業管理を見直すきっかけにしてください。
【コラム公開】年次有給休暇の付与・管理と時季指定義務
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 年次有給休暇の付与・管理と時季指定義務
労働者が心身のリフレッシュや私用の処理などを目的に取得する年次有給休暇は、労働基準法で強く保護されています。とりわけ、2019年の法改正で「年5日の有給休暇の時季指定義務」が企業に課せられ、従業員に少なくとも5日は有給休暇を取らせることが義務付けられました。
しかし、実際には「有給休暇が取りにくい職場」や「消化義務をどう管理すればいいか不明」など、企業側の対応に悩みが多いことも事実です。本記事では、年次有給休暇の基本ルールや付与日数、管理簿の作成、違反時のリスクなどを整理します。自社の有給休暇管理のご参考となれば幸いです。
【コラム公開】休日の設定と週休2日制の注意点
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 休日の設定と週休2日制の注意点
従業員の労働時間を適正に管理するうえで、休日をどのように設定し、管理するかは非常に重要です。労働基準法では、少なくとも週に1日は法定休日を与える義務が企業に課されています。最近は「週休2日制」が一般的になってきましたが、実際には「法定休日」と「所定休日」の区別を正しく理解していないケースもあり、結果的に休日労働の割増賃金計算にミスが生じることもあります。
本記事では、休日設定の基本ルールや週休2日制を導入する際の注意点、シフト管理のポイントを解説します。休日労働の割増賃金をめぐるトラブルを防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。
【コラム公開】裁量労働制(専門型・企画型)の留意点
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 裁量労働制(専門型・企画型)の留意点
裁量労働制とは、従業員の労働時間を実際の働いた時間ではなく、あらかじめ定めた時間を「みなし」としてカウントする制度を指します。研究開発や高度専門業務、企業の企画業務などに携わる従業員が自律的に時間を使えるようにする目的で導入されるケースが多いですが、その対象業務や導入手続きは労働基準法で厳しく限定されています。
本記事では、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の違いや導入要件、運用上の注意点などを解説します。制度を誤って導入してしまうと未払い残業代のリスクが高まり、企業に大きな負担がかかる恐れがあります。裁量労働制を検討中の企業の皆さまのご参考となれば幸いです。
【コラム公開】変形労働時間制導入の要件と実務
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 変形労働時間制導入の要件と実務
企業によっては、業務量が多い時期と少ない時期がはっきりしている、あるいは曜日ごとに来客数が大きく変動するなど、一定ではない稼働状況があります。そんなときに有効な手段のひとつが「変形労働時間制」の導入です。
通常、労働基準法は「1日8時間・週40時間」を上限としていますが、変形労働時間制を導入すると、繁忙期に労働時間を長めに設定し、閑散期に短くするなど、平均して週40時間に収まれば合法という制度設計が可能です。
しかし、導入には労使協定の締結や就業規則への定めなど、いくつかの要件を満たす必要があります。本記事では、1年単位・1カ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などの特徴や要件、実務での注意点をまとめました。
変形労働時間制導入を検討中の方にとってご参考となれば幸いです。
【コラム公開】管理監督者と割増賃金の適用範囲
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 管理監督者と割増賃金の適用範囲
残業代の支払いに関して、「管理監督者は時間外・休日・休憩の規定が適用されない」という労働基準法の規定をご存じの方は多いでしょう。しかし、実際にはどの程度の権限や待遇があれば管理監督者と認められるのかは、法律上も明確な基準が設けられておらず、裁判所の判断に委ねられるケースが少なくありません。
本記事では、管理監督者と割増賃金の適用範囲をテーマに、法的な定義や判例上の基準、実務で注意すべき点を解説します。実態が伴わないまま「管理職だから残業代は不要」としてしまうと、名ばかり管理職問題に発展し、多額の未払い残業代が請求される可能性があります。
店長や管理職を置く企業の皆様は、ぜひ参考にしてください。
【コラム公開】残業代請求訴訟の防止策
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 残業代請求訴訟の防止策
企業と従業員との間でトラブルになりがちなテーマの一つが、未払い残業代です。特に、近年は労働者の権利意識が高まっており、残業代請求訴訟や労働審判に発展するケースが増えています。一度裁判等に突入すれば、企業側には大きなコスト・リスクがのしかかるだけでなく、企業イメージの悪化も免れません。
そこで本記事では、残業代請求訴訟を防ぐために企業が実施すべき対策を詳しく解説します。労働時間管理の徹底や適法な賃金体系の整備、社内コミュニケーションの重要性など、実務に役立つ情報をお伝えします。残業代トラブルを未然に防ぎたい経営者・人事担当者の皆様にとってご参考となれば幸いです。
【コラム公開】解除条項と改定手続きで失敗しないために|継続契約の見直しポイント
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 【契約更新・再交渉】解除条項と改定手続きで失敗しないために|継続契約の見直しポイント
企業間の取引契約は、一度締結して終わりではなく、長期にわたり継続するケースが多々あります。例えば数年ごとに更新が行われる販売代理店契約やライセンス契約など、契約満了のタイミングで更新するか、解除するか、条件を再交渉するかといった重要な意思決定が求められます。このプロセスを適切に管理しないと、意図しない自動更新や不十分な再交渉で企業が不利を被る可能性があります。
また、契約期間中に紛争や業績不振が発生し、中途解除や再交渉が必要になる場合もあり、契約解除条項が曖昧だと高額な損害賠償を請求されるリスクもあります。本記事では、契約の更新・解除・再交渉を行う際に注意すべき条項設定や手続きを解説します。継続契約を安全に運用し、企業にとって最良の選択を確保するための要点を押さえましょう。
« Older Entries Newer Entries »